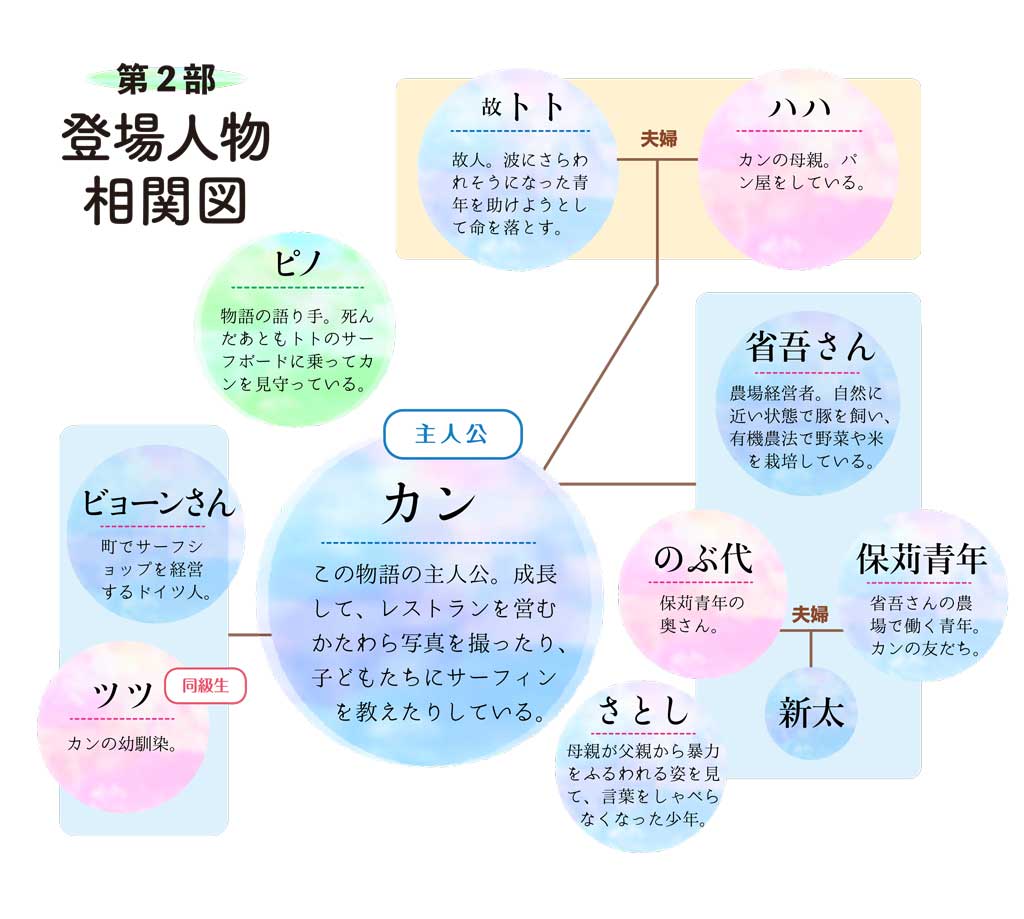第6話
たった一個のパンが
2022年03月09日号
カンの人生がずっと順調だったわけではない。勉強のほうは時計を使った訓練によってかなり改善された。また小学校のあいだは、ほとんどの科目で暗記カードが通用した。しかし中学から高校へと進むにつれて、記憶力だけでは切り抜けられないことが多くなった。
波乗りをはじめたのは高校に入ったころだった。ハハに基本を教えてもらったあとは、自分で練習して少しずつ上達した。休みの日には海で長い時間を過ごした。楽しむというよりは、海の上に居所を見つけようとしているみたいだった。
そんなとき大波がやってきた。学校の勉強がうまくいかなくなって、さすがにあの子も疲れてしまったのだろう。朝から風が強く吹く日だった。午後には海は大荒れになった。こんな日に波乗りをするのは正気の沙汰ではない。
夜になってから一人で海に出た。あいかわらず海は荒れ狂っていた。案の定、少し沖に出たところで波に呑み込まれた。わたしは岸から一部始終を見ていた。あっという間のことだった。カンの身体は海に引き込まれた。助けに行きたくてもどうしようもない。
いよいよダメかと思ったとき、不意に風がおさまり、雲の切れ間から丸い月が出た。明るい月の光が、荒れた海を宥めるように照らしていた。そこにポツンと一枚の板が浮かび上がった。つづいて波のあいだからカンの頭が現れた。彼はボードをつかんで身体を引き揚げると、水を掻いて岸をめざしはじめた。

あのときカンの命を救ったのはトトだ、とわたしは思っている。きっと暗い海のなかで声が聞こえたのだ。それとも月だろうか。いつかトトは言っていた。海は月を感じている。月が海を持ち上げるように、あの子の身体も上げてくれたのかもしれない。
外国へ行くことを勧めたのはハハだった。無理に大学に進む必要はない。言葉が喋れないなら、最初から言葉が通じない外国へ行ってしまえばいい。
ハハ自身にも同じ体験があった。大学生のときに、とてもつらいことがあった。外国に行けば気分が変わると思った。残念ながら、そう簡単にはいかなかった。どこへ行っても楽しくない。何を見ても心が動かない。あるときドイツの小さな町に泊まった。古い宿の粗末な部屋でベッドは固く、シャワーのお湯はいつまでも温かくならなかった。
「翌朝、食堂で出されたパンにバターをつけて、ひと口齧ったときに何かが変わったの。カチッと音をたててスイッチが入ったみたいだった」
なんの変哲もないパンだったという。その味は一生忘れられないものになった。たった一個のパンが、人に生きる勇気を与える。同じことがカンにも起こってほしい、とハハは願ったのだろう。