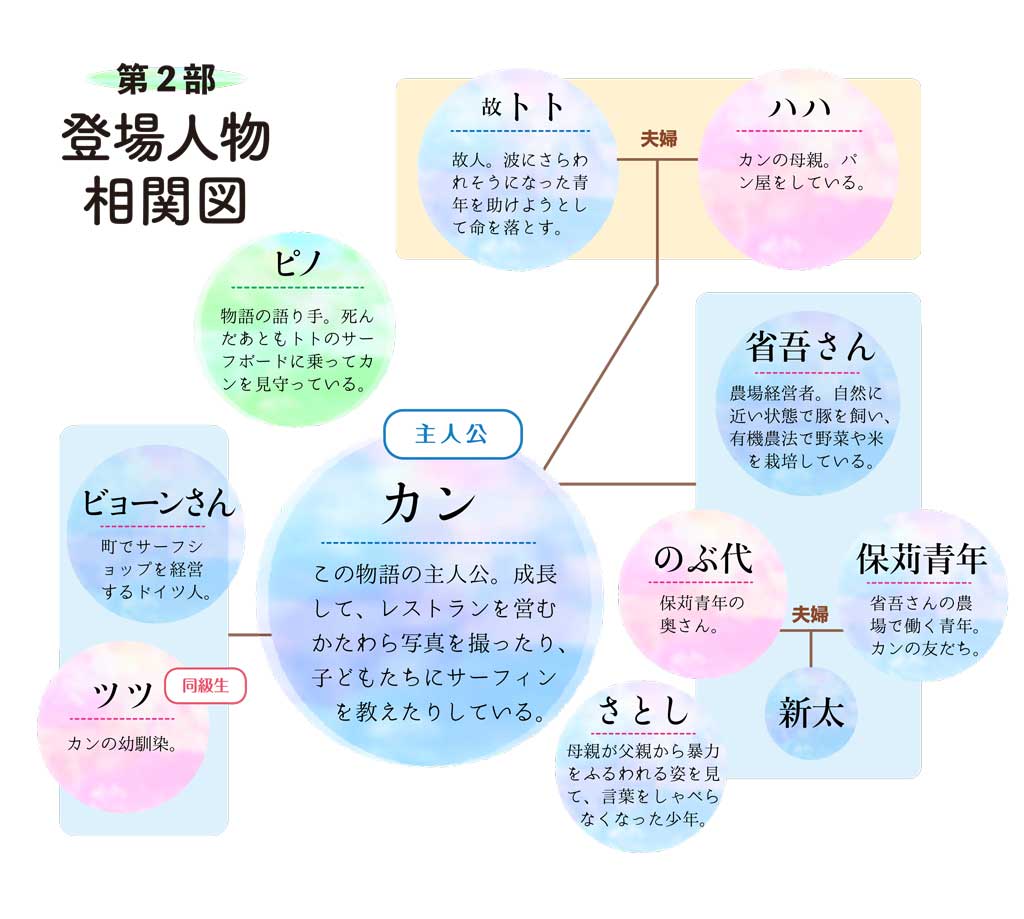第8話
ビョーンさんのこと
2022年03月30日号
ドイツ出身のビョーンさんが、この町でサーフ・ショップを営むことになったいきさつは、彼を知る人たちのあいだでは一つの伝説になっている。
理学療法士であった彼が日本にやって来たのは十年ほど前だ。火山が好きだったので、各地のそれらしい山をまわっていた。たまたま訪れたところが想像していたイメージとは違ったので、早々につぎの場所をめざすことにした。移動手段はヒッチハイクである。何時間も道端に立ちつづけ、ようやく乗せてもらった車にはサーフボードが積んであった。
サーファーとともに町へやって来たビョーンさんは、勧められるまま海に入った。十一月だというのに、水はまだ充分に温かかった。ドイツの海は夏でももっと冷たいらしい。すっかり気に入って、しばらく滞在することにした。
車に乗せてくれた青年が、地元のサーフ・ショップを紹介してくれた。店の主人は四十過ぎの男で一人暮らしをしている。もともとサーフィンが好きで店をはじめたのに、気ままに波乗りができないのが悩みの種だった。せっかくいい波が立っても、店にいなくてはならないことがある。そこでビョーンさんを店番として雇ってくれることになった。満足な給金は払えないが飯は食わしてやる。狭いけれど部屋も空いている、ということだった。

こうして町に居つくことになったビョーンさんは、数年前にハワイへ移住した主人から店を受け継ぎ、いまは地元の仲間たちにも助けられて、サーフ・ショップの他にスクールを運営している。通常は生徒数人に一人のインストラクターが付いてサーフィンを教える。スクールはシーズンを通して開かれており、少々の雨でも海さえ荒れていなければ大丈夫だ。
カンも子どもたちに波乗りを教えることがある。そんなときはビョーンさんの世話になる。店には気温や季節に応じてさまざまなサイズのスーツが揃っている。
二人が親しくなったのは、ビョーンさんが外国人で片言の日本語しか喋れなかったせいかもしれない。いまでは流暢に日本語を操るビョーンさんだが、最初のころは言葉のレパートリーが少なく、食堂に入っても「ご飯、味噌汁、から揚げ」くらいしか注文することができなかったそうだ。
ここの暮らしを気に入ったのは、一年中サーフィンのできる海があり、新鮮な野菜と美味しい肉・魚があり、温暖な気候で物価も安いからだ。加えて親切な人たちがいる。
ビョーンさんを見ていると、人はみんな同じだなと思う。肌の色や育った環境は違っても、誰もが一回きりの人生を送っている。それをいちばんいいかたちで送りたいと考えている。