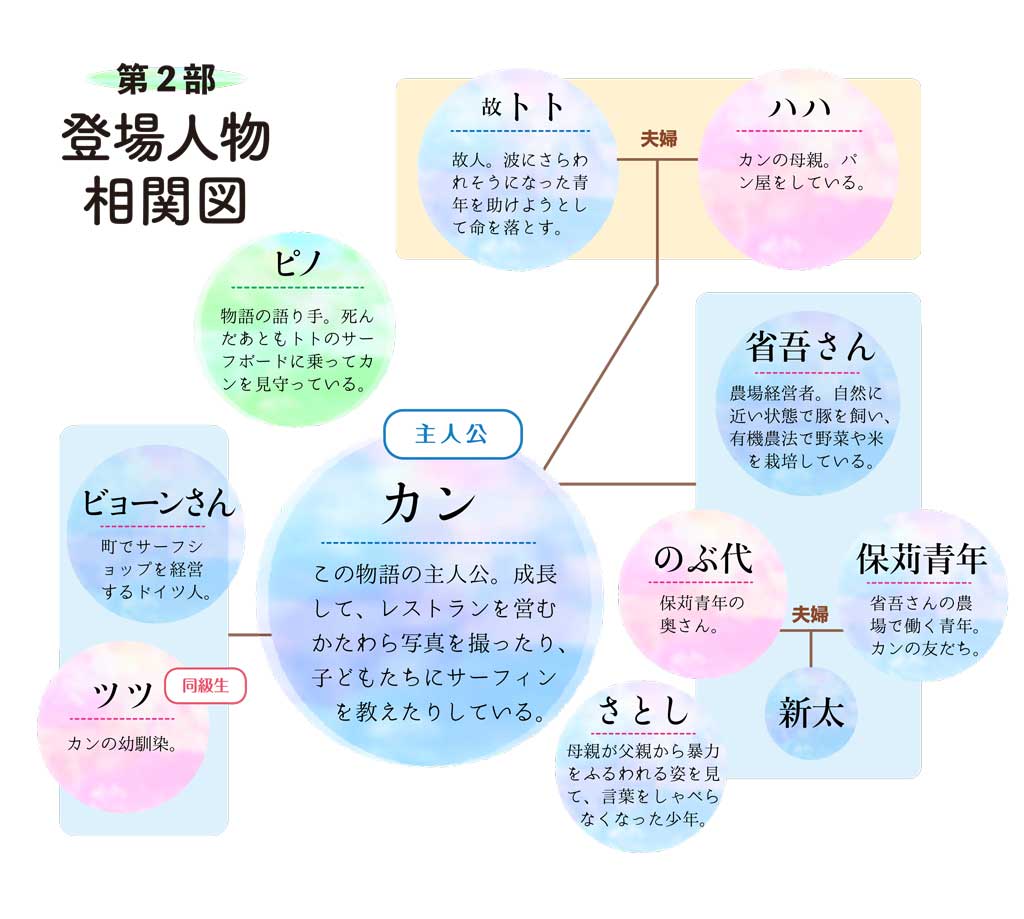第17話
誰も見たことがなかった世界
2022年06月29日号
少年は店に入ってきたときから、小さなゲーム端末を操作している。両手の親指でめまぐるしくボタンを押しつづけて片時も休むことがない。小学三年生というから、さとしよりも二つほど下になる。
「いつもこうなんです」。母親は困ったように言った。「無理に取り上げようとすると泣き叫んで抵抗するんです」
保育園のときから、みんなと一緒に座っていることができなかった。いつも一人で遊び、何も感じていない様子だった。小学校では授業に参加するのが難しくなった。基本的な指示には従うものの、感情表現がほとんどなく、まわりで起こっていることを気にかけない。誰かが身体に触れると、全身の力をふりしぼって叫びつづける。
「一つだけ集中できるのがゲームなんです」。そう言って、母親は大きなため息をついた。「狙撃ゲームっていうんですか、倒した相手の数やスピードを競うゲームらしいんですけど」
カンは医者やカウンセラーではないから、何かアドバイスをするわけではない。もともと無口なので、黙って話を聞いているだけだ。分析も解釈も価値判断もしない。そんな様子に、かえって相手は安心するのかもしれない。若い母親は重い口を開いて悩みを打ち明けはじめた。
「きっと居心地がいいんだろうと思います。高得点をあげて注目されることもあるらしいので。でも将来のことを思うと心配になります。あんなに没入していると、そのうちゲームから出てこられなくなるんじゃないかって」

人間がいろいろなものを発明するのも考えものだと思う。ゲーム機がなければ、あの少年だって自分の居場所を見つけただろう。本のなかとか、自然のなかとか……そう考えると、のぶ代さんの「えほんの郷」は前途多難かもしれない。ゲームに夢中になっている子どもを、絵本の世界に連れてくるのは難しいだろう。虫を捕ったり魚を釣ったりするのも、そのうちゲームのなかでやるようになるかもしれない。
〈夜明け前の海で波を待っていたときのことです。海の向こうから、朝が近づいてくるのが感じられました。海面が輝きはじめます。でも太陽はなかなか顔を出してくれません。どのくらい時間が経ったでしょう。ふと何かが顔をかすめたようでした。誰かが耳元で言葉にならない言葉をささやいて通りすぎたみたいでした。
つぎの瞬間、それは姿を現しました。ぼくが発見するまで、誰も見たことがなかった世界。海の上や自然のなかでは、そんなことがよく起こります。何かを発見したとき、そこは前とは少しだけ違ったところになっています。〉