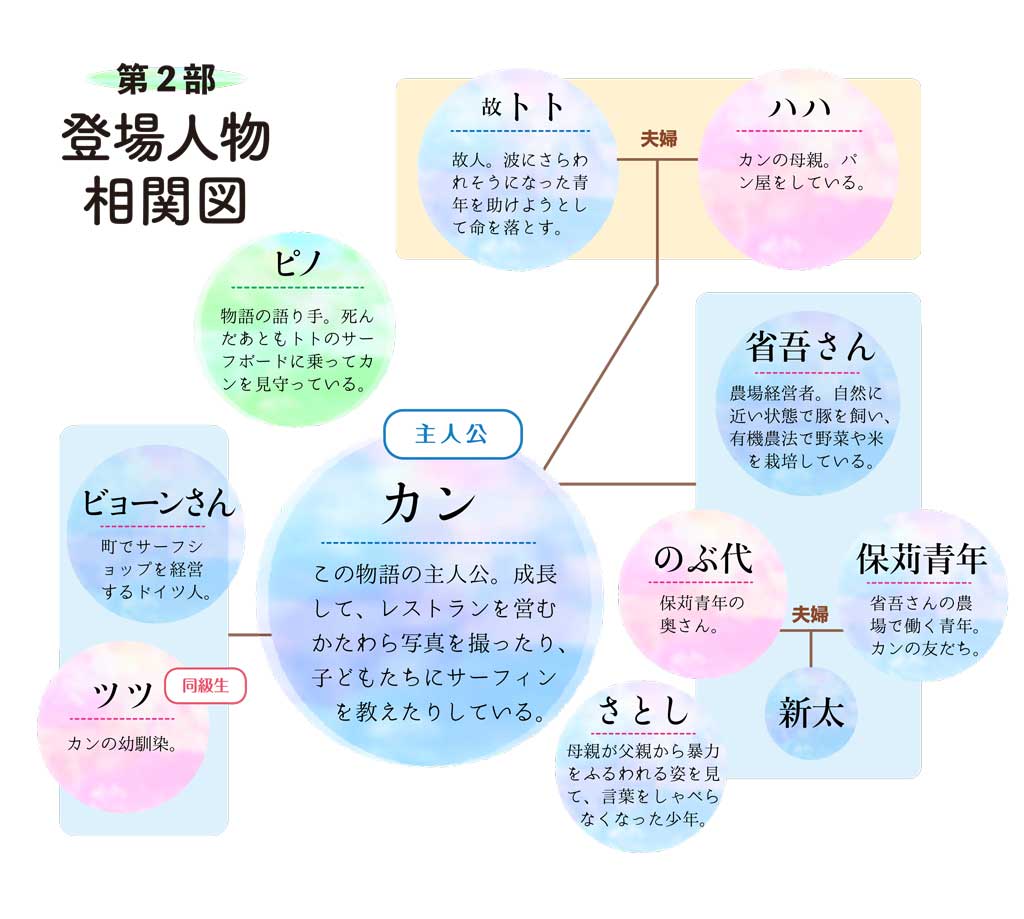第21話
心を打たれる光景
2022年08月10日号
午後からカンは、さとしを農場へ連れていった。事情を聞いている省吾さんは、少年を豚の餌やりに誘った。
「ここの豚は食べる力を自分で手に入れていく。与えられる飼料を食べているだけじゃあ、生きる力は身に付かない。生きる力っていうのは、要するに生き延びる力だ。わかるか?」
言葉の勢いに押されたという感じで、さとしはうなずいた。
「いいことを教えてやろう。おまえの両親を無人島へ連れていく。ロビンソン・クルーソーって知ってるか?」
今度はさっきよりもしっかりとうなずいた。
「ああいう絶海の孤島に放り込まれたら、その日のうちに食べ物の心配をしなきゃならない。鳥を獲ったりカメを獲ったり、野生の山羊を飼い慣らしたり。喧嘩などしている暇はない。うすぼんやりした生ぬるい現実のなかで生きているから、つまらないことにうつつをぬかすんだ」
省吾さんはしばらく考え込んだ。
「まあ、おまえにこんなことを言ってもしょうがないな。とにかく生き延びなくちゃならない。そのために生きる力を身に付けることだ」
わかったような、わからないような話を切り上げて、省吾さんはどこかへ行ってしまった。あとはカンが引き受けた。言葉を喋らなくなった少年と、かつて言葉を喋らなかった青年が、いまは一緒に農場のなかを歩いている。それは不思議と心を打たれる光景だった。

この世界にはいろんな人が暮らしている。カンは言った。みんな苦労して生きている。貧しい国も多い。外国を旅していると、なんだか自分の悩みがちっぽけなものに感じられた。
外国へなんか行きたくない。さとしは言った。ずっとここにいて、カンと一緒に暮らしたい。
ぼくはずっとここにいる。ここで料理を作ったり、写真を撮ったりしている。そしてときどき、さとしのことを考える。どこで暮らしていても、さとしはひとりじゃない。
少年の目から涙が溢れた。胸を締め付けられる思いとともに、わたしのなかに甦ってくる情景があった。ベッドで眠っている少年のカンは、ときどき夢にうなされることがあった。閉じられた目から溢れた涙は、頬を伝って静かに流れた。
かつてのカンの涙を、いまはさとしが泣いている気がした。どうやらパンによっても涙によっても人はつながるものらしい。おいしいことと悲しいことは、人間にとって同じ意味をもつのかもしれない。ちなみに犬は涙を流さない。そのことを残念と思ったことはない。