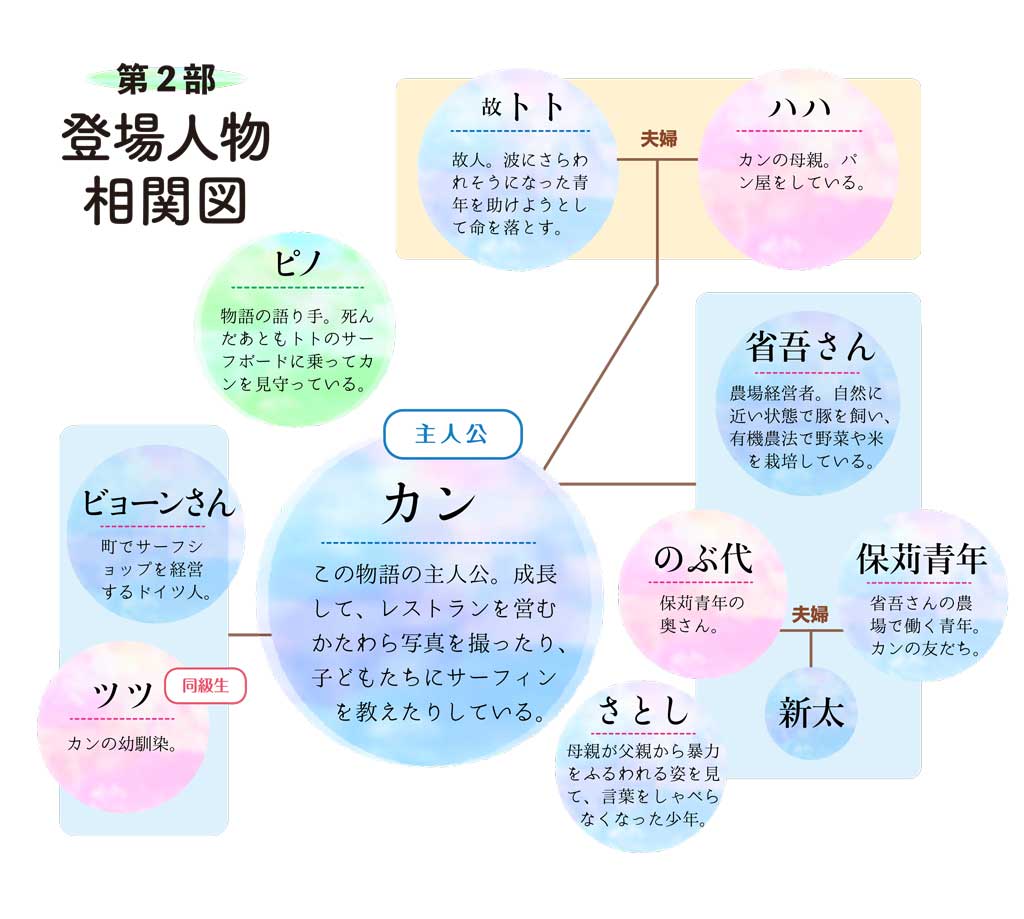第22話
変わっていくチャンス
2022年08月24日号
カンのレストランに保苅青年とのぶ代さん、ハハの四人が集まった。外は雨が降っている。店のなかには三拍子のピアノ曲が流れている。恒例の夕食会だが、いつものように話ははずまなかった。雨のせいばかりではないだろう。
さとしと母親は、省吾さんのところに身を寄せて何日か過ごしたあと、支援センターの相談員やソーシャルワーカーの仲介によって、夫とは離れたところにアパートを借りて生活することになった。今後は継続的な援助を受けながら、法律や弁護士の力を借りることになりそうだ。
「あの人の話を聞いていると、こっちまで元気がなくなってくる」。のぶ代さんが悲しそうに言った。「無力感って伝染するのかもしれない。安易に同情しちゃいけないって思った」
カンは新しい料理を用意するために席を立った。料理はすでに調理してあり、あとは温めるだけだ。陶器の器のなかで、海老とキノコがオリーブオイルとニンニクで煮込んである。
「頭にくるのは、暴力がかならず弱い者に向けられること」。のぶ代さんは先ほどとは口調を変えて言った。「連れ合いには暴力を振るう亭主も、会社の上司を殴ったりはしないわけでしょ?」
「二人になると人は違ってくるから」。

ハハは料理を小皿に取り分けながら言った。「さとし君のところも、お父さんという一人の人間を見れば、悪い人じゃないのかもしれない。でも夫婦のなかでは、悪い人になってしまう」
「夫婦や親子でもそうなんだから、他人が大勢集まった社会がうまくいかないはずですよね」。のぶ代さんは言った。
言葉が途切れているあいだに、ハハが流れている音楽のことをたずねた。「リパッティ」とカンが答えた。ピアニストの名前らしい。
「はじまっていない人なのかもしれないな」。保苅青年がひとりごとみたいに言った。
のぶ代さんはもの問いたげに夫を見た。
「ぼくがそうだったから」。彼は店の音楽に耳を澄ますような表情で言った。「どうやって自分をはじめればいいのかわからなかった。そして、はじまらない自分を壊そうとした。さとし君のおとうさんは、自分を壊すかわりに他人を攻撃しているのかもしれない」
のぶ代さんは困ったようにハハを見た。「でも生きているんだから」。ハハは穏やかな声で言った。「生きているかぎり、いつでもはじめることができる。変わっていくチャンスがある」
わたしにはハハが、死んだトトのことを想っている気がした。