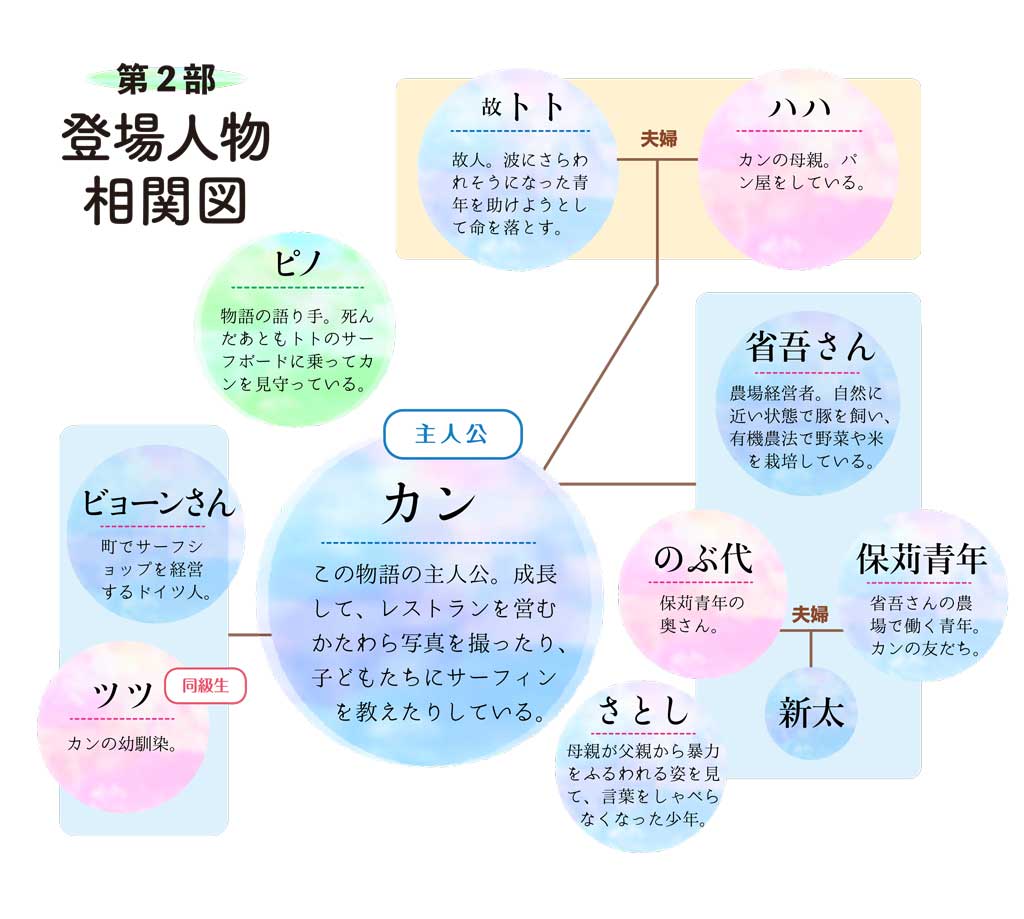第26話
「えほんの郷」を訪れる子どもたち
2022年09月28日号
夏休みになると、日に何人かの子どもたちが「えほんの郷」を訪れるようになった。一人でやって来る子もいれば、絵本好きの親に連れてこられる子もいる。懐かしがって古い絵本を手に取る母親の傍らで、息子はスマホでゲームをしたりしている。
お菓子や飲み物を持ってくる子もいる。そんな子にたいしても、のぶ代さんは何も言わない。ここでは大人は口出しをしない。彼らはときどき子どもたちの心を重くする。だから親も先生もいない、そんな空間が必要だと思っている。
「いまの子どもたちって、なんだかつらそう。つらさを紛らわすために、ゲームばかりやっているのかもしれない。ここを子どもたちの心が軽くなるような場所にしたいの」
小学校の先生が、児童を連れてやって来ることもある。絵本に興味を示す子もいれば、まったく示さない子もいる。犬のなかにも、飼い主と遊ぶのが好きなやつもいれば、そうでないやつもいる。犬も人間もいろいろということだろう。
「泣いている子がいるわけ」。その日の出来事を、のぶ代さんは保苅青年に報告することにしている。「どう見ても悲しい話じゃないのにね。何かに感動したってわけでもなさそう。なぜかわからないけど涙が出てくる。絵本って、そういうものかもしれない」
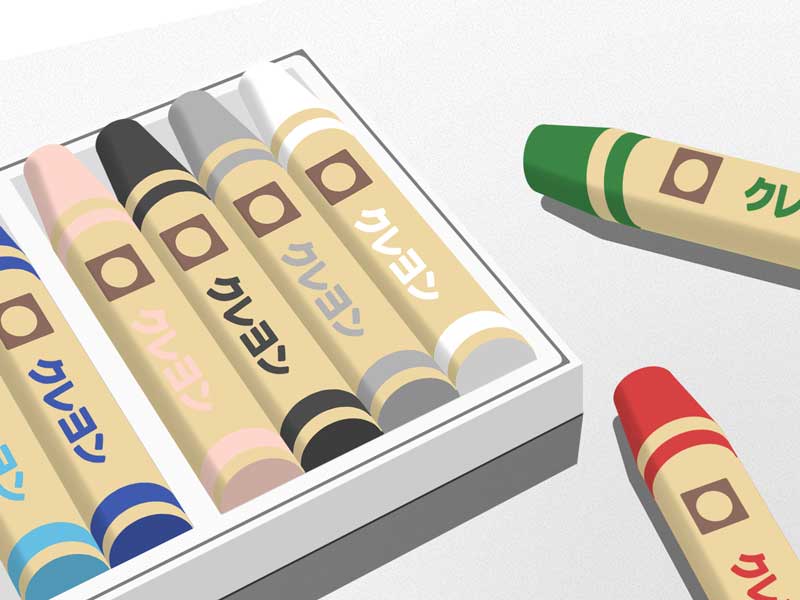
あるとき思い立って、子どもたちが絵本を読む部屋に、画用紙、クレヨン、クレパス、色鉛筆などの画材を置いてみた。すると絵本を読むのに飽きた子どもたちが絵を描きはじめた。それまでゲームばかりしていた子も加わったりする。
子どもたちの絵についても、のぶ代さんは何も言わない。「よく描けてるわね」などと言うこともない。絵はそのまま置き去りにされる。子どもたちがいなくなってから、彼女は画用紙を集めて、絵を一枚ずつ見ていく。そして静かに微笑む。
子どもたちには、学校の勉強以前に教えなければならないことがある。何かを発見する喜び。不思議なことに反応できる感性。小さな生き物や役に立たないものを温かく見守るやさしさ。
文字など読めなくてもいいのかもしれない。たくさん言葉を知っている必要はないのかもしれない。新太を見ていると、そんな気がしてくる。あの子はなんにでも興味をもつ。自分のまわりのものを注意深く見ている。目に入るものはなんでも喜びに変えてしまう。大人も子どもも、新太のように生きればいいのだ。