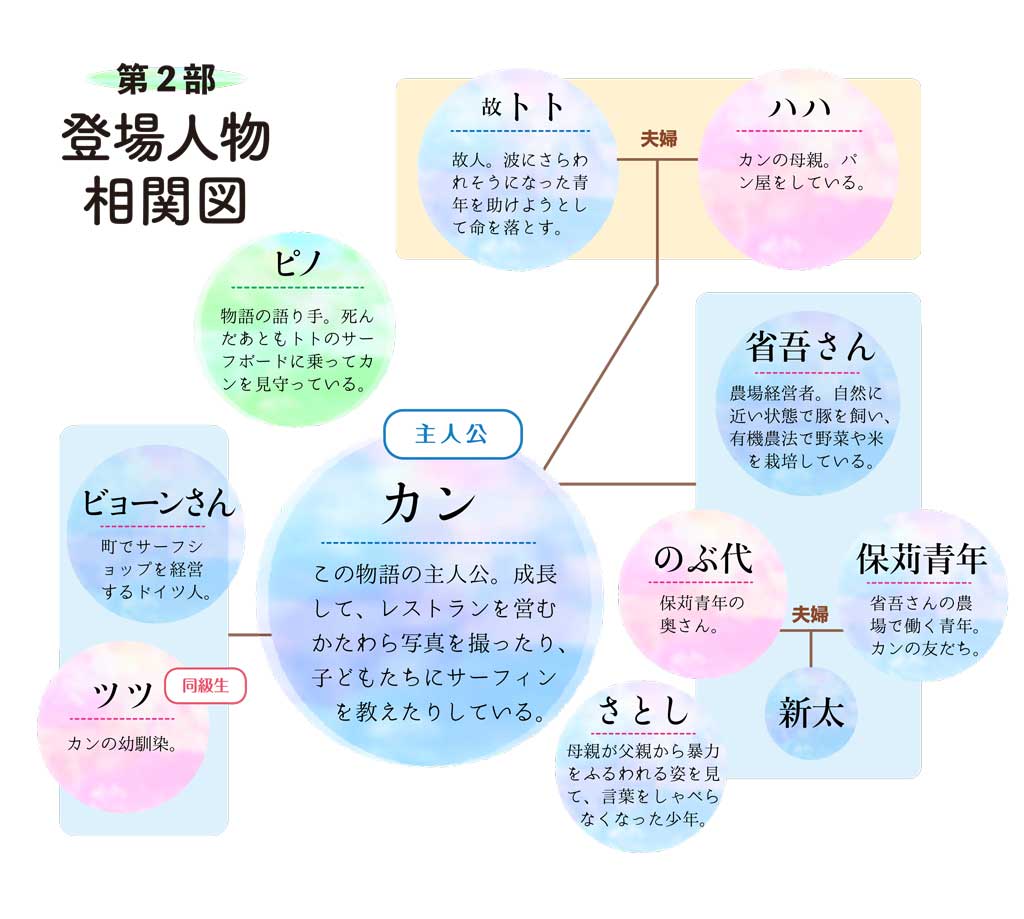第30話
誰のものでもない命
2022年11月09日号
農場はいつになくひっそりとしていた。いま新太はベッドの上で手術を待っている。のぶ代さんと保苅青年は病院に詰めている。
省吾さんが豚に餌をやっていた。将来は新太に任せたいと思っている仕事だ。
「人間に飼われている豚のほとんどは、生まれてすぐに母親から引き離され、ろくに太陽も浴びないまま配合飼料を与えられ、大きくなったところで肉にされる。そのうち天罰がくだるな」
彼の怒りが豚を飼う人間に向けられているのか、新太を苦しめている病気に向けられているのかわからない。きっと両方だろう。省吾さんのなかで、新太と豚は切り離せない。新太にとっても、豚は大切な友だちだ。
「動物にやさしくするのは大切なことだ。動物が苦しんでいる姿を見て、かわいそうだと思う。助けてやりたいと思う。その気持ちが大事なんだ。新太はいい魂をもっている。だから何があっても大丈夫だと、おれは信じている」
カンは必要な野菜を自分で収穫して店に戻った。ランチの下ごしらえをしていると、ハハが焼き上がったばかりのパンを持ってきた。いつもと変わったところはないけれど、何かが大きく違っていた。二人は無言で支度をつづけた。それぞれが自分の思いにとらわれているみたいだった。一人の子どもに取り憑いた病気が、まわりにいる大人たちの日常を、色も音もないものにしていた。

その日、カンは午後から新太の見舞いに出かけた。本人に会うことはできなかった。のぶ代さんや保苅青年と少し言葉を交わしただけで病院を後にした。
〈大切な友だちが生と死の境をさまよっています。幼い友だちの死を、ぼくは思い描くことができません。彼はまだ四つになったばかりです。生の果てに訪れるという死。年老いるまで生きた人にとっては、そうかもしれません。でも、ようやく生きはじめたばかりの子どもに訪れる死とは、なんでしょう? そんなものに意味があるとは、どうしても思えません。
考えて、考えて、さらに考えているうちに、頭が自分を離れてしまいました。おかしな言い方ですが、本当にそんな感じでした。ぼくは病院の待合室にいました。窓の向こうに目をやると、庭木の緑が太陽の光に輝いています。どこでも目にする、ありふれた景色です。でも、そのとき木の葉も太陽も、自分とともに息をしていると感じました。
命が自分を生きている。命が命を生きている。束の間、死はぼくから離れていました。この世界から出ていって、どこにもありませんでした。誰のものでもない命があるような気がします。〉