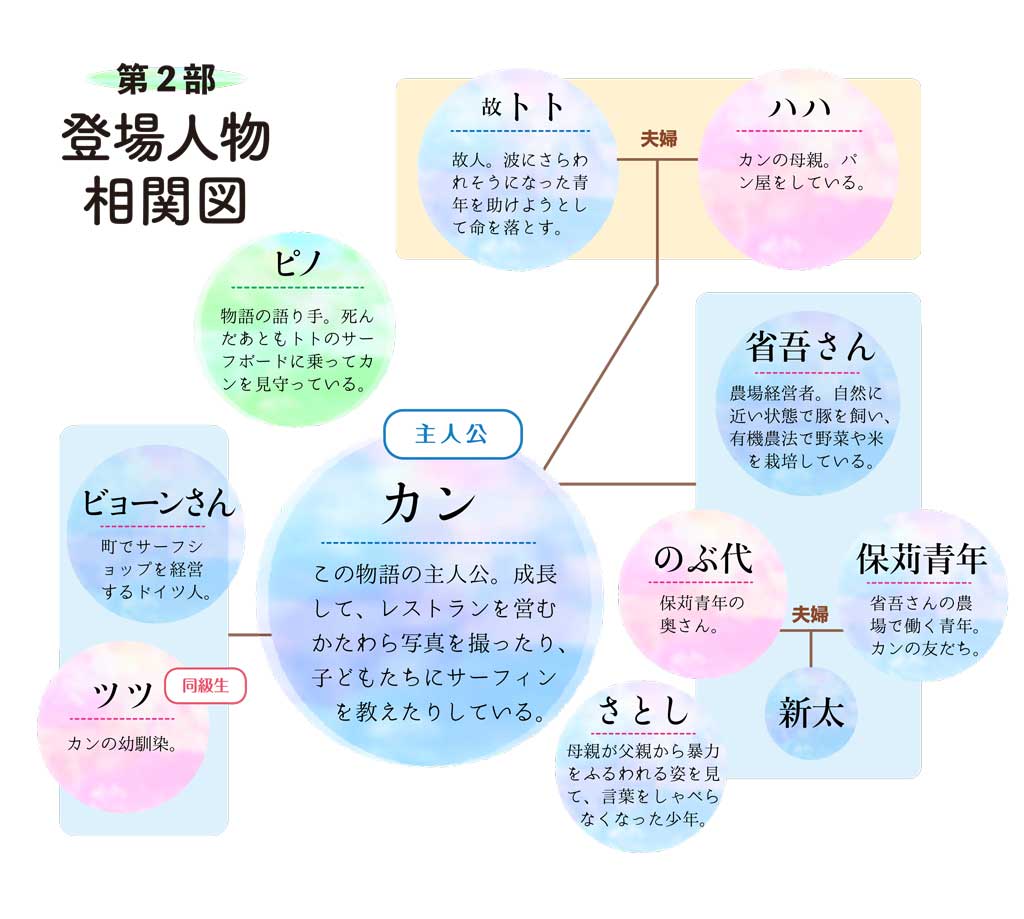第36話
遠くからもたらされた「贈り物」
2023年02月01日号
保苅青年は腕組みをして畑を見渡した。自家製の堆肥をたっぷり施した畑では、ズッキーニやゴーヤ、ナスなどの夏野菜が収穫のときを迎えていた。
「ここの野菜はあまり形が良くない」。彼は真面目な口調で言った。「どことなくバランスが悪くて不格好だ。だから、かわいいのかもしれない。小さな子どもと同じで」
「たしかに、あまりに均整のとれた子どもって、かわいくないかも」。ツツが笑いながら言った。
「ちょっと虫食いしているけど、無農薬だから」
保苅青年は収穫したばかりの野菜が入った段ボール箱をツツに渡した。
「ありがとう」と彼女は言った。
初対面であるはずの二人は、まるで古くからの知り合いみたいだった。
「子どもを育てるのも、野菜を育てるのも、同じことかもしれないな」。しばらくして保苅青年は言った。
「前にカンに話したことがあるけど、中学生のころから、どうして自分が生きているのかわからなかった。理由もないのに生きていたってしょうがない。そんなことを思い詰めて、なんとなくここへやって来た」

「いまは?」。ツツは遠くを見たままたずねた。
「贈り物のように感じる。どこか遠くから、もたらされたような気がする」
農場から帰りの車のなかで、ツツは外を見たまま何か考え込んでいるみたいだった。
「風を手でつかめそうな日がある」。彼女は誰にともなく言った。「今日はそんな気分」
カンはハンドルを握ったまま、助手席のほうにちらりと目をやった。
「いい言葉だね。贈り物って」
田んぼでは稲の穂先が色づきはじめていた。その傍らに車を停めて、カンは胸のポケットから一通の手紙を取り出した。この街を離れたばかりのころ、ツツが彼に宛てたものだ。
「わたしって、こんなだった?」。読み終わると、彼女はちょっと照れくさそうに言った。「まるで自分じゃないみたい」
カンは戻ってきた手紙を丁寧に折りたたんで、元のように封筒に収めた。
「でも、これがわたしだったんだ」
彼女は遠いまなざしを田んぼのほうへ向けた。
「もうすぐ稲刈りだね」