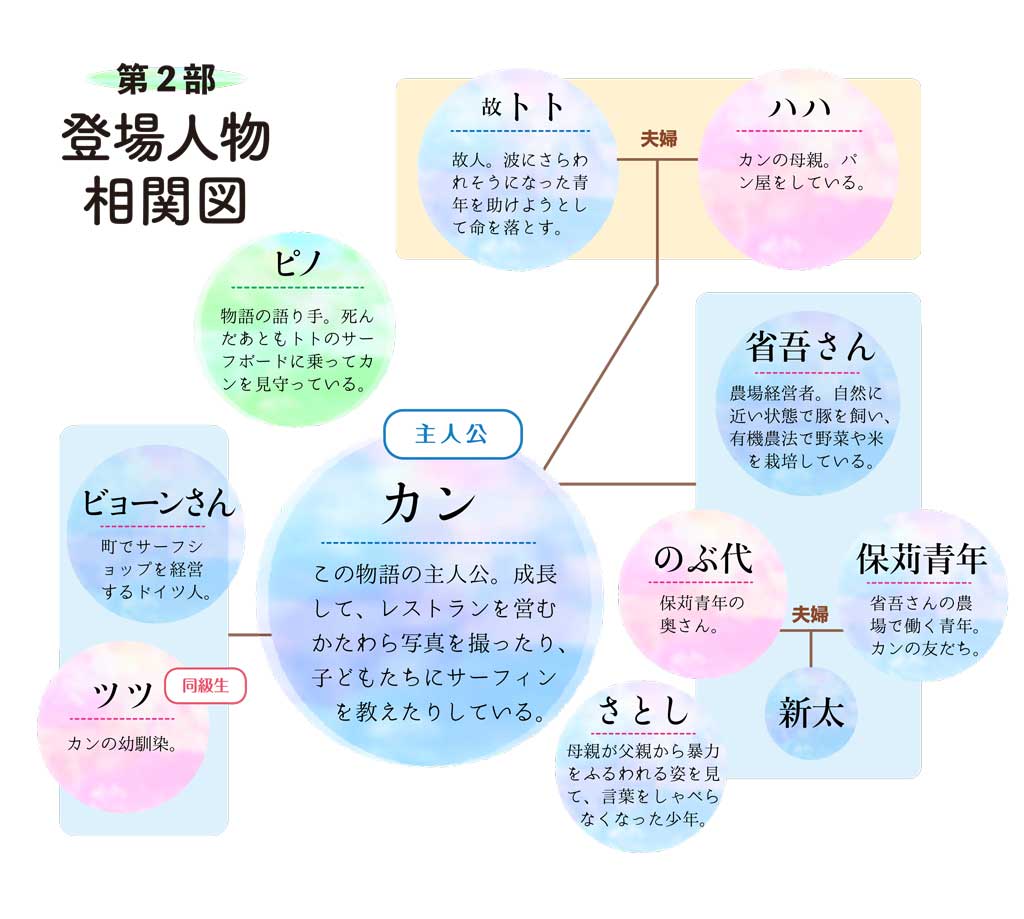第7話
月の光に照らされて
2022年03月23日号
ときどきカンは夜中に目を覚ます。手早く服を着替えて家を出る。車を走らせてトトが好きだったビーチへ向かう。
二月は半ばを過ぎていた。菜の花が田んぼや川の土手を黄色く彩りはじめるころだった。春に向かいはじめたところで、季節が戻ってまた寒くなった。カンはセーターの上に厚手のダウン・ジャケットを着込んでいる。
風はほとんどなく波は静かだった。満月に近い月が海を照らしている。道路わきの草原に車を乗り入れた。エンジンを切ると、たちまち車のなかは寒くなった。運転席に坐ったまま、しばらく海を見ていた。月が光を投げると、海がそれに答える。そうやって月と海は言葉を交わしている。
トトが呼んでいる気がする夜には、あの子の心もトトに会いたがっている。そんなときは、ここにやって来る。この海の見える場所で、二人は密やかな言葉を交わす。
「やあ、元気にしているかね」
「うん。そっちはどう?」
わたしは二人のやりとりに耳を澄ます。もちろん言葉は当人たちにしか聞こえない。でも誰かが耳を澄ましていることが大切なのだ。すると天上の星々や、地上の草や木や動物たちが話しはじめる。言葉をもたないと思われているものたちが、自分たちの言葉を交わしはじめる。

「年に一度か二度、不思議な小鳥に出会うことがある」。いつかハハは言った。「ムクドリとかジョウビタキとか……普通に見かける鳥なんだけど、その鳥は、いつまでも立ち去ろうとせずに、ずっとそばに居つづけるの。そんなときは、トトが会いにきてくれたんだなと思う」
カンはぼんやりした顔でハハの話を聞いている。大切な話を聞くときは、いつもこんなふうだ。相槌も打たずに、見た目はぼんやりしている。人によっては頼りないと思うかもしれない。でもハハには、ちゃんとわかっている。あの子の心は旅に出ているのだ。大切な話は、ここから遥か遠いところに、ひっそりと息づいている。それはハハが出会った小鳥が住まっているところかもしれない。
雪が降りはじめていた。それこそ年に一度か二度の雪だ。暗い空から、月の光に照らされて白い花びらみたいな雪が落ちてくる。この雪は誰の化身だろう? 誰が誰に会いに来ているのだろう?
「さあ、そろそろ帰ったほうがいい」
あの子は車のエンジンをかけようとしない。もうしばらく、ここにいたいのだ。花びらの数はどんどん増えて、やがて夜空を覆い尽くすだろう。