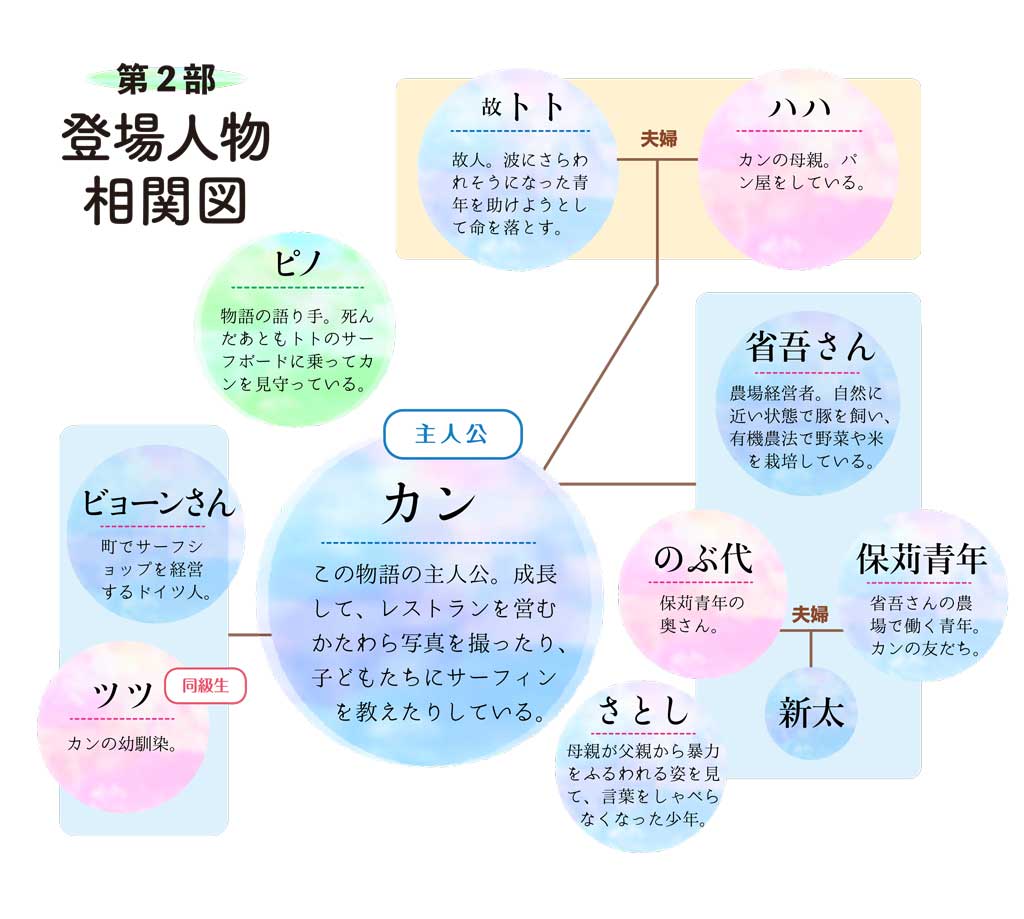第9話
自分の居場所を探して
2022年04月13日号
サーフィンを習うといっても、水に入っているのはせいぜい二時間くらいだ。あまり長くやると疲れるし、集中力も途切れてしまう。
子どもたちのなかには、最初は海に入るのを嫌がる子もいる。とくに春先は海の水もまだ冷たい。親に連れられてしぶしぶやって来た子などは、まるで面白くなさそうな顔をしている。そんなときカンは一人で海に入り、ボードで遊びはじめる。
彼がサーフィンを気に入っているのは、面倒なルールがないせいかもしれない。海と自分のあいだには板切れが一つあるだけだ。あとは好きにしていい。誰から文句を言われることもなく、自由に波と戯れることができる。しかし波には波の都合があって、なかなか思いどおりにはいかない。そこが面白いらしいのだが、犬のわたしには理解できない心境だ。
子どもも人間の一員だから、やはり面白いと思うらしい。浜辺でぐずぐずしていた子も、楽しそうに波と戯れているカンを見ているうちに、その気になるようだ。頃合いを見て誘うと、おずおずと海に入ってくる。

最初はカンも一緒にボードに乗る。つぎにボードの上に腹這いになって水を掻くことを教える。パドリングというらしい。そうやって子どもたちは、海と上手に付き合うことをおぼえていく。自分で水を掻いて好きなところへ行ってもいいし、疲れたらボードに跨って休んでいればいい。穏やかな波の上で揺れているのは、いかにも気持ちがよさそうだ。
やがて子どもたちはボードの上に立とうとしはじめる。早い子はあっという間だ。むしろ付き添いの親たちのほうがもたもたしている。子どもたちが波乗りの真似事をはじめるころに、スクールの時間は終わりになる。彼らの顔に失望が広がる。もっとつづけたいのだ。
でも今日はここまで。無理は禁物だ。またつぎに教えてあげる。海はなくならないし、ぼくはいつでもここにいるから。
子どもたちは無口で物静かなカンになんとなく安心するのかもしれない。不服そうだった子も、最後は納得して帰っていく。ほとんどの子の顔が、来たときよりも少しだけ明るくなっている。
ここには学校や家庭とは別の世界がある。そんなことを冷たい水の感触とともに、子どもたちは感じ取るのかもしれない。彼らが探しているのは自分の居場所なのだろう。それがあの子にはわかっている。カン自身が、かつてそうだったから。