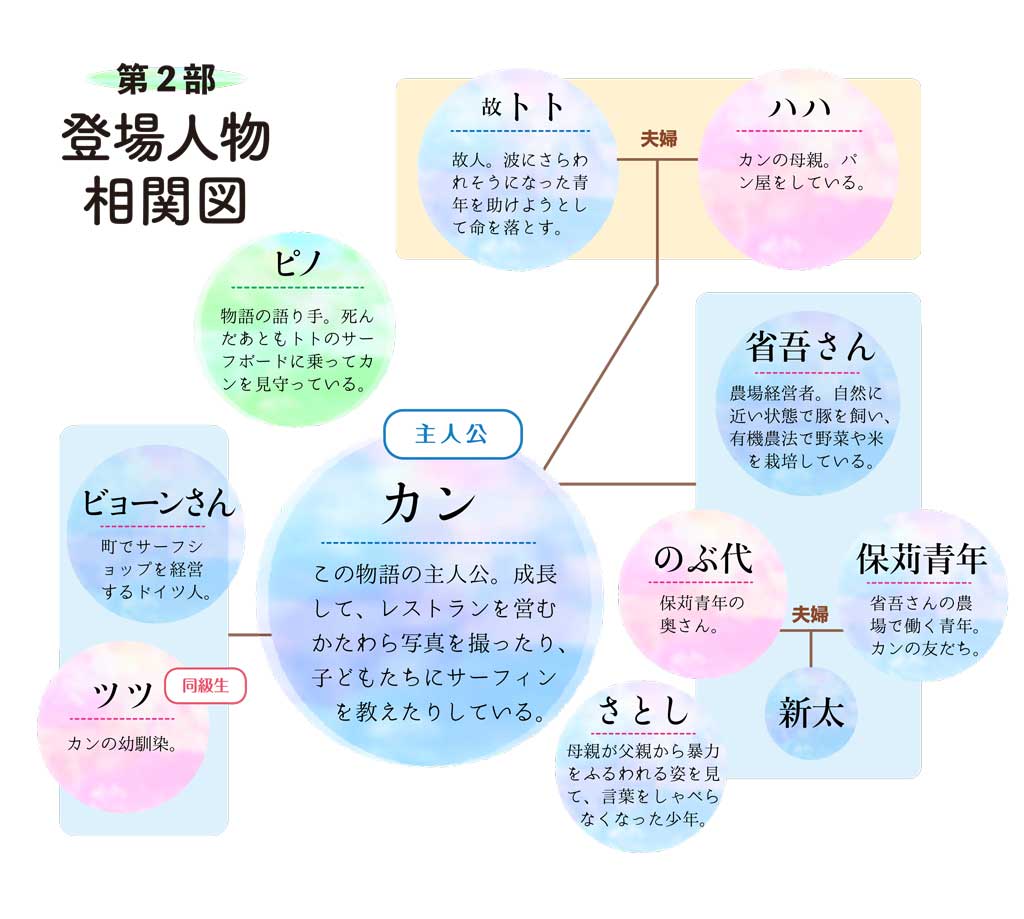第10話
言葉を喋らない少年
2022年04月20日号
はじめて会った相手をじっと見つめるやつがいる。反対に目を合わせようとしないやつもいる。合わせてもすぐに逸らせてしまうやつ。
きっと普通の育ち方をしなかったのだろう。子犬のころにいじめられたとか、狭い小屋のなかに閉じ込められて、ろくに散歩にも連れていってもらえなかったとか。そんなやつらは自分がどこかへ行ってしまう。
この少年もそうだった。店に入ってきたときから、うつむいたまま顔を上げようとしない。他人と目が合うことを恐れているようにも、いま自分がいる世界を拒んでいるようにも見えた。
わたしはトトを亡くしたばかりのころのカンを思い出した。虚ろな目をして歩きまわりながら、あの子もまた行方不明になった自分を探していたのかもしれない。
カンは店をハハにたのんで二人を海に誘った。自分の車に乗せて、手近なビーチをめざした。冬の海は少し波立ち、太陽の光に輝いている。何人かのサーファーたちが波乗りをしていた。多くはボードに跨って波を待っている。冬の日差しはありがたい。海に入って波乗りをする連中にとって、太陽は冷えた身体を暖めてくれる大切な相棒だ。身体が暖まれば心も温まる。
少年は波打ち際からサーファーたちを見ていた。冬のやわらかな日差しが彼を包んでいる。母親とカンは少し離れた砂地に腰を下ろした。

母親は自分たちの身に起こったことを話しはじめた。そんなことがときどきある。ほとんど見ず知らずと言っていいカンを相手に、長く心の奥にしまっていたことを打ち明けはじめる。そういう不思議な力が、あの子にはあるらしい。
少年の父親は大手企業のサラリーマンだった。母親とは職場で知り合い、結婚を機に彼女のほうは仕事をやめた。背が高くスポーツマンタイプの夫は、会社では女性社員のあこがれの的だった。そんな相手と一緒になれた自分は幸せだと思った。
結婚して半年くらい経ったころから、夫はこれといった理由もなく大声でどなったり物を投げつけたりするようになった。ある日のこと、はじめて軽い暴力を振るった。会社で何かあったらしい。同じようなことが繰り返された。そのたびに彼女のほうは、この人も苦しいのだと思って我慢した。しかし理由のわからない子どもは情緒不安定になった。学校で落ち着かなくなり、授業中に突然大声を発したり、教室のなかを走りまわったりするようになった。それが収まると、今度は言葉を喋らなくなった。
「ブログであなたの文章を読みました」。母親は波打ち際のわが子に目をやったままで言った。「一度お会いしてみようと思って」