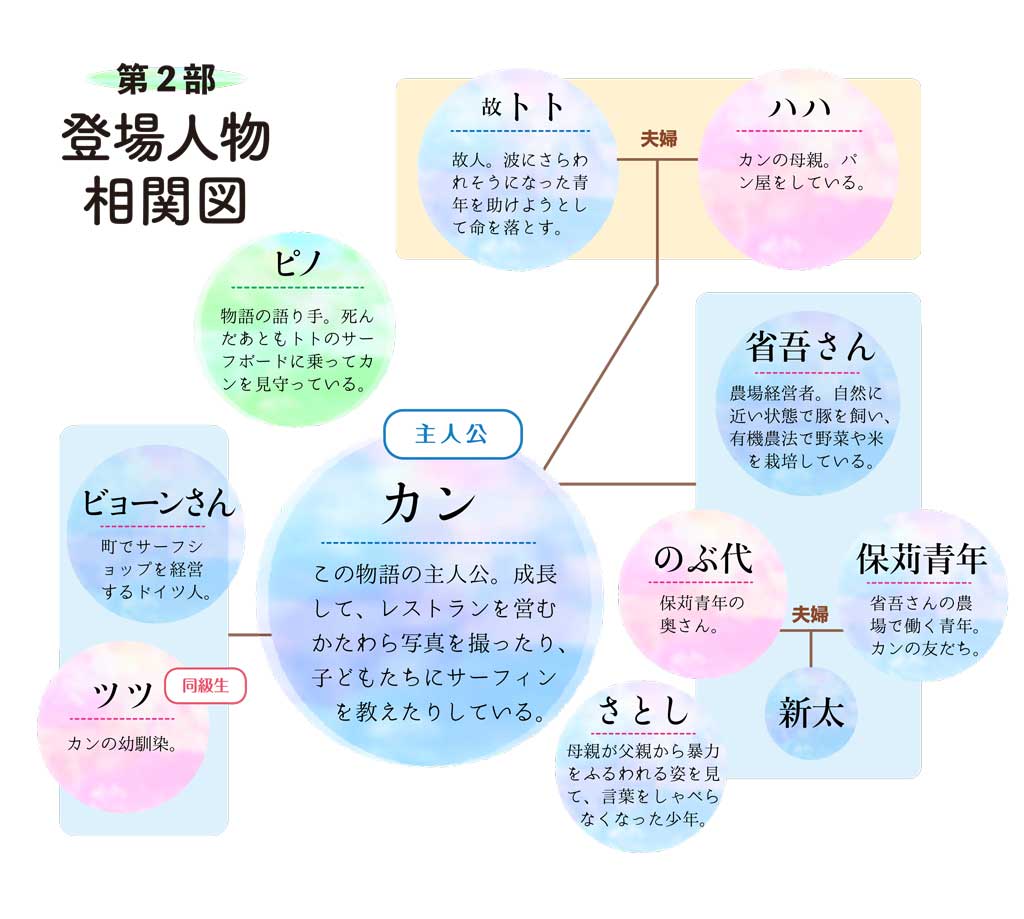第35話
夜眠れない人がいる
2023年01月18日号
夕暮れまでにはまだ時間があるはずなのに、外はすっかり暗くなっている。やがて雷が鳴り、雨が激しく降りはじめた。
カンとツツはとりあえずビョーンさんの店先に避難した。店の前は、サーフボードを乾かしたりするためのウッドデッキになっていて、日差しを遮るテントが付いている。そこに二人は並んで腰を下ろした。雨はかなり降り込んでいるけれど、短パンにTシャツのカンも、ジーンズにタンクトップのツツも気にする様子はない。
「なんだか心のなかにも降り込んでくるみたい」
ツツは雨のことを言った。それからちょっと困ったように笑った。
「ハハは元気?」
カンはいまの自分たちの暮らしのことを話した。彼が話し終わると、今度はツツが話しはじめた。サユリさんは大学の非常勤講師で、主に英語を教えている。週に何日かは、知り合いの店でピアノを弾く。フウちゃんも打楽器奏者として活躍している。プロのミュージシャンたちのライブやレコーディングに呼ばれることもあるという。
「ときどき通訳の仕事もしているの。アフリカの言葉が話せるので重宝がられているみたい。日本語ができない外国人が起こした事故や事件で、警察から協力を求められることもあるんだって」
言葉をおいて、彼女は薄い灰色のカーテンがかかった海に目をやった。

「ここで暮らしていたころは、夜眠れない人がいるなんて信じられなかった。わたしなんてベッドに入った途端に意識がなくなって、朝まで夢も見なかったから。健康優良児の見本みたいだったのにね」
大学を卒業したあと、ツツは日本の外資系企業に就職した。両親はすでに日本に戻っていた。英語が堪能であることを見込まれての採用だったが、仕事は通常の事務と変わりなかった。英語を使う機会はほとんどなく、むしろ日本人の女性社員よりも、言葉の上でハンディを負うことになった。転職も考えたけれど、親しく付き合っていた会社の同僚との結婚話が進んでいた。彼に引き留められるかたちで会社に残りつづけた。
しだいに疲労を覚えるようになり、強い不安にも襲われた。夜は眠れなかった。医者の診察を受けると、ストレス性のものと言われ、適度な運動を勧められて睡眠薬を処方された。別のところでも同じことを言われた。そのうち病院にも行かなくなった。
「薬を飲んだって眠れないんだもん」。彼女はいくらか投げやりに言った。「夜のあいだずっと起きていて、昔のことをいろいろ思い出しているうちに、急にカンに会いたくなったの」
冗談めかした言い方だったけれど、事態はかなり深刻そうだった。