
第4話
頭のなかの積み木
2020年08月02日号
小学校に上がる前に、カンは都会の大きな病院で頭のなかを調べてもらった。言葉が出ない原因はわからなかったが、これといった異常は見当たらないとのことで、トトとハハはひとまず安心した。
「そのうち喋るようになるかもしれないしね」
「大きくなったら一流のサーファーになるかもしれないぞ」
二人とも呑気な性格なので、喋らなくてもサーフィンはできるし、波にぶつかっても死ぬことはないと思ったのかもしれない。
学年が上がるとともに、物にぶつかる回数は少なくなったものの、あいかわらず言葉を喋ることはなかった。加えて厄介な問題が出てきた。先生が黒板に書いた文字や数字をノートに書き写すと、文字も数字も鏡に映したように左右が反対になってしまうのだ。全神経を集中して書いても、ノートの上の文字や数字はかならず反対向きになっている。
そのため学校の成績は芳しくなかった。とくに苦手なのは算数だった。足し算のやり方がわからないので、数字をでたらめに選んでは何がなんだかわからないままに足した。もちろん答えは間違っている。カンは算数が嫌いになった。それで算数の時間になると教室を抜け出し、体育館の裏やプールの陰などに隠れることにした。
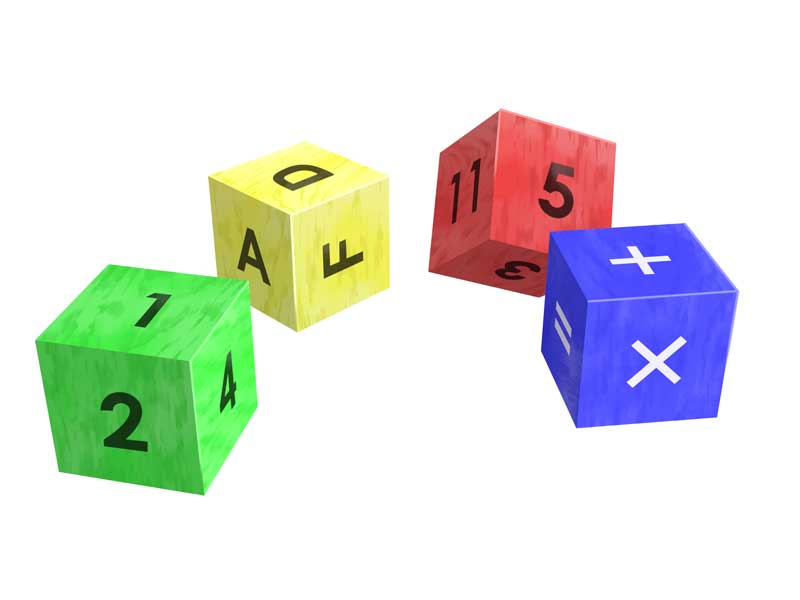
トトは内科医なので、風邪を引いたときやおなかの調子が悪いときには頼りになるが、足し算ができない原因については見当がつかなかった。二人は息子を再び大きな病院に連れていき、専門の先生に診てもらうことにした。
「たぶん心に何か障害物があるのでしょう」
「障害物というと?」
「ブロックみたいなものと考えてください」
三人は腕組みをしたまま黙り込んだ。話を聞きながら、カンは自分の頭のなかには積み木が入っているのだと思った。どうしてそんなものが入ったのかわからない。しかし足し算ができない原因については、はっきりした。積み木のせいだ。
ある日、いつものように算数の授業を抜け出して、中庭の大きな松の木の陰に隠れていると一人の女の子がやって来た。
「驚いた。なんでこんなところにいるの」
女の子の肌は運動場の土よりも少し濃い茶色で、髪は釣り糸がもつれたように絡まってボール状になっている。
「何か言いなさいよ。日本語がわからないの?」
のちにわかったことだが、彼女の名前はツツ。外国の暮らしが長かったために読み書きが苦手で、国語の時間になると教室を抜け出してくるのだった。とくに今日は大嫌いな作文なので、授業終了のチャイムが鳴るまで、教室には絶対に戻らないつもりだった。

